次のトピック
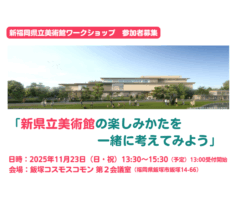
お知らせ
新福岡県立美術館ワークショップ「新県立美術館の楽しみかたを一緒に考えてみよう」(筑豊地域)の参加者を募集します!(募集は終了しました)
2025.10.14
2025.09.12
来るべき新県美に向けて、県美の「これまで」を育み「これから」をつくっていく様々な方のお話を伺っていく連載『県美と新県美』。
第2回目となる本記事は、福岡県立美術館で現職活躍中の三名の学芸員にお話を伺いました。
[参加者]
高山 百合(たかやま・ゆり)
福岡市出身。平成24年福岡県立美術館学芸員として採用。近代洋画を担当。現在は福岡県立美術館学芸課副長。趣味はジョギング、1年に1度はフルマラソンを走ることにしている。現在はこの秋に開催の「没後50年 髙島野十郎展」の準備にいそしんでいる。
岡部 るい(おかべ・るい)
京都府出身。平成27年福岡県立美術館学芸員として採用。現在は、近現代美術担当として学芸業務に従事。趣味は野鳥観察。
中島 由実子(なかじま・ゆみこ)
島根県出身。平成30年福岡県立美術館学芸員として採用。日本画、工芸を主に担当。趣味は漫画、ゲーム、手芸、生き物を愛でること。髪の色はコロコロ変わる。

【取材日:2025年2月28日|聞き手:三好剛平(三声舎)】
——まずは皆さんお一人ずつの自己紹介と、福岡県立美術館でお仕事を始められたきっかけを教えてください。
高山さん 学芸員の高山です。福岡県立美術館には2012年度に就業しましたので、いま勤続14年目になりますかね。この業界では地元育ちの学芸員って案外珍しいんですが、私はここ福岡、博多の出身で、九州大学大学院で勉強しました。専門は近代洋画で、当館でも所蔵されている九州出身作家の明治、大正、昭和戦前期あたりの作品を研究していましたので、学んできたことをそのまま活かすことができているのは感謝ですね。実は学生時代に「没後30年 髙島野十郎展」(2005)を実際にこの美術館で見ていまして、それが県美に入ったきっかけというのでもないんですが、まさか自分がその美術館に入って、10年後には「没後40年 髙島野十郎展」(2015)に携わることができたことは、すごく縁を感じます。

岡部さん 学芸員の岡部です。専門は近現代美術です。2015年に福岡県立美術館の学芸員として着任し、今年で10年目です。私は外国語大学の出身で言語畑出身です。専攻はロシア語で、ロシア芸術ゼミで学んでいました。院生の時に国立国際美術館(大阪)でインターンを2年間、その後、研究補佐員として3年間従事し、同館では現代美術のほか多くのことを学びました。その後福岡県立美術館にやってきました。

中島さん 学芸員の中島です、よろしくお願いします。島根県松江市の出身で、大学は九州大学で、高山さんの後輩にあたります。そこから気がついたら福岡在住も10年を超えました。大学院生の時に県美でアルバイト募集がありましたので1年間働いた後に、たまたま運良く正規採用の試験があるとのことで、改めて試験を受け2018年に採用。現在、勤続7年目、バイト時代を含めればプラス1年という具合です。もともと大学では戦前ぐらいまでの日本画を研究していましたが、県美に入ってからの専門は、前任者が工芸の担当だったこともあり、工芸と日本画を両方担当させてもらっています。

——続いて、皆さんのこれまでのお仕事のなかで、特に記憶に残っている展覧会があれば、お聞かせください。まずは高山さんから。
高山さん これまで色んな展覧会をさせていただいて、どの展覧会も印象に残っているもので上下はつけられないんですが……、強いて言うならば、2017年度に開催した「没後50年 中村研一展」を挙げたいと思います。学芸員の職について6年目ぐらいに担当した展覧会で、それまでは先輩に手取り足取りご指導いただいていたところから、色んなものを吸収させていただき、やっと少し独り立ちしてもいいのかなと自信が持てたという意味でも、非常に印象深い仕事になりました。
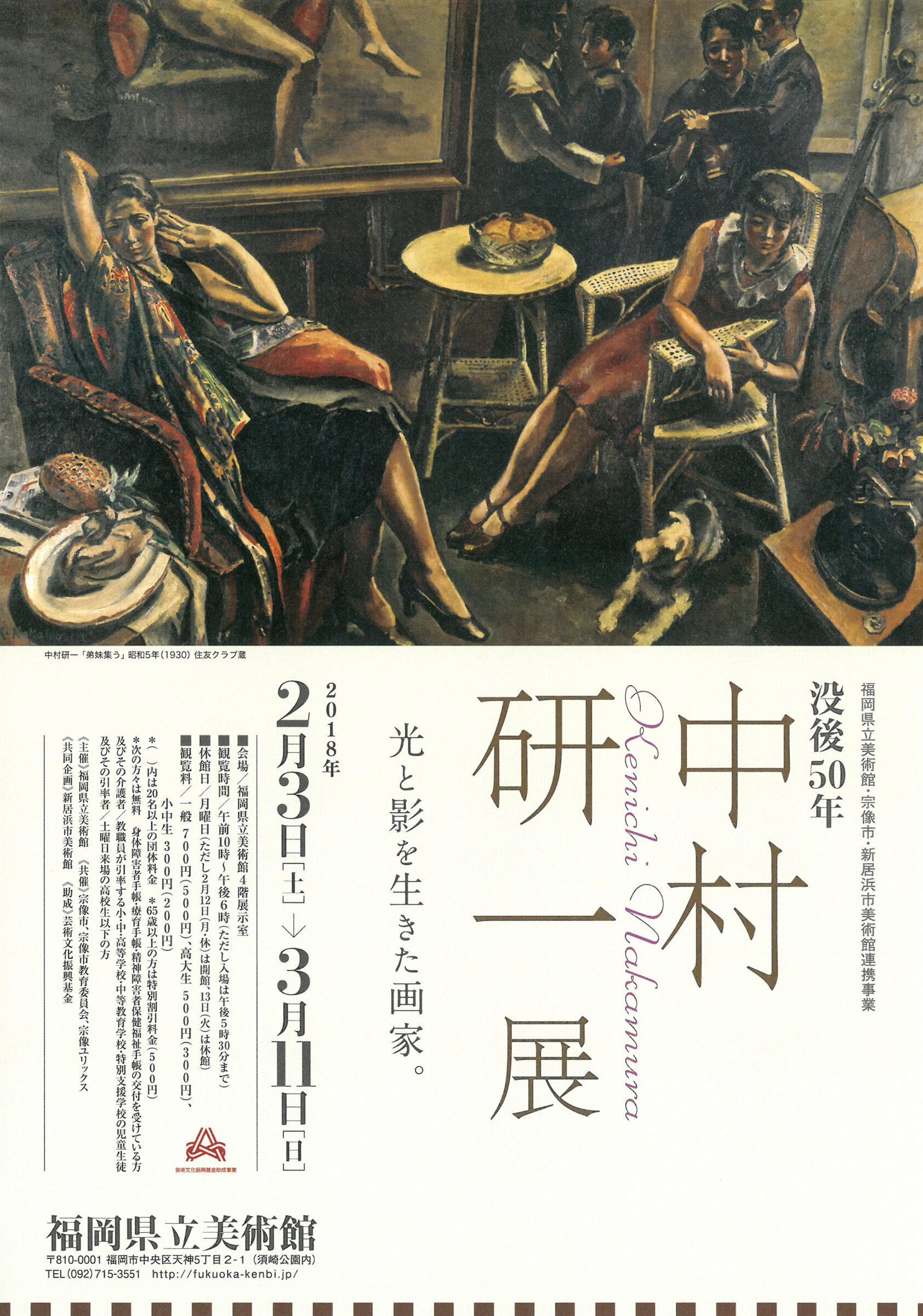
実はこの美術館の前身にあたる福岡県文化会館でも「中村研一遺作展」(1972)という展覧会が、昭和47年に開かれていました。そこからおよそ45年ぶりの中村研一展ということもありまして、先輩の学芸員の方々が残してくださっていた貴重な古い資料を夜な夜な引っ張り出してみたり、たくさん眠っていたネガフィルムを見ながら、作品の情報や所在を調べました。さらに、彼の地元である宗像で、中村研一のことを大事に思い続けていらっしゃる方々と出会えたことも大きかった。「展覧会をやること」の向こう側にある、単に作品や資料を集めて調べることに限らない人々との関わりというか、その難しさと楽しさを両方感じた展覧会で、今でもすごく記憶に残っています。
——続いて、岡部さんはいかがですか?
岡部さん 高山さんと同じく、どの展覧会も記憶に残っているので一つを挙げるのは難しいですね。「豊福知徳寄贈記念展 光の探求」(2022)と「寄贈記念展 野見山暁治」(2022)は、いずれも寄贈を契機に企画した展覧会を挙げたいと思います。「寄贈記念展 野見山暁治」に関しては、野見山暁治さんの晩年、お元気な時期に開催できました。何度も会場にお越しくださりさまざまなお話を伺うことが出来ました。


——新規収蔵に対するご予算も限られるなか、美術館にとってはそうしたご寄贈がもたらすものはかなり大きいのではないかと思いますが、いかがですか?
岡部さん 寄贈は非常に有り難いものですが、寄贈をお受けすることはやはり大きな責任を感じます。事前の作品調査は、多岐に渡り時間をかけて行います。作品調査だけでなく、受入れるためには状態の確認や適切な保存方法の検討も重要です。未来に引き継いでいかなければなりませんから。収集方針に基づいて寄贈をお受けした作品、いいえ、寄贈に限りませんが、作品を守りながらいかに鑑賞機会を充実させていくかについて常に考えさせられます。

——中島さんの印象に残っている展覧会は、いかがでしょうか?
中島さん 印象の残り方にも、「大変だった」から「やり切った」まで様々ありますね(笑)。私がはじめて関わらせてもらった展覧会は「鹿児島寿蔵の人形と短歌」展(2018)で、もちろん印象に残っていますが、それはもう前回記事で魚里さんがお話くださっているので、そちらに譲るとして。

もうひとつ印象に残っているのは「1964—福岡県文化会館、誕生。」(2021)で、はじめて私が図録から何まで任せてもらえた展覧会でした。
企画した当時は2020年の東京オリンピック開催を控え、また新県美の構想も具体化し始めていた時期でもありましたので、1964年の東京五輪と(県美の前身である)福岡県文化会館の開館が同年だったことを基点として、その歴史を振り返るような展覧会として準備を進めていました。しかし新型コロナの影響で開催が1年間延期になったうえに、やっと開催できた後も2週間で終了することとなりました。展示が宙吊りになっていた期間にも、旧文化会館時代の職員さんなどに改めてお話を伺ってみたり、動画を作ってみたりとか色々したのも自分にとっては忘れ難い経験になりました。
やっぱりさっきの高山さんの「中村研一展」もそうですけど、諸先輩方が資料を色々残してくださっていたので、その中から私は面白そうなものを選んで、編ませてもらったという感覚が大きいですね。実はこの展覧会は、近いうちにリバイバル展として改めてお届けできそうなので、ご期待ください。
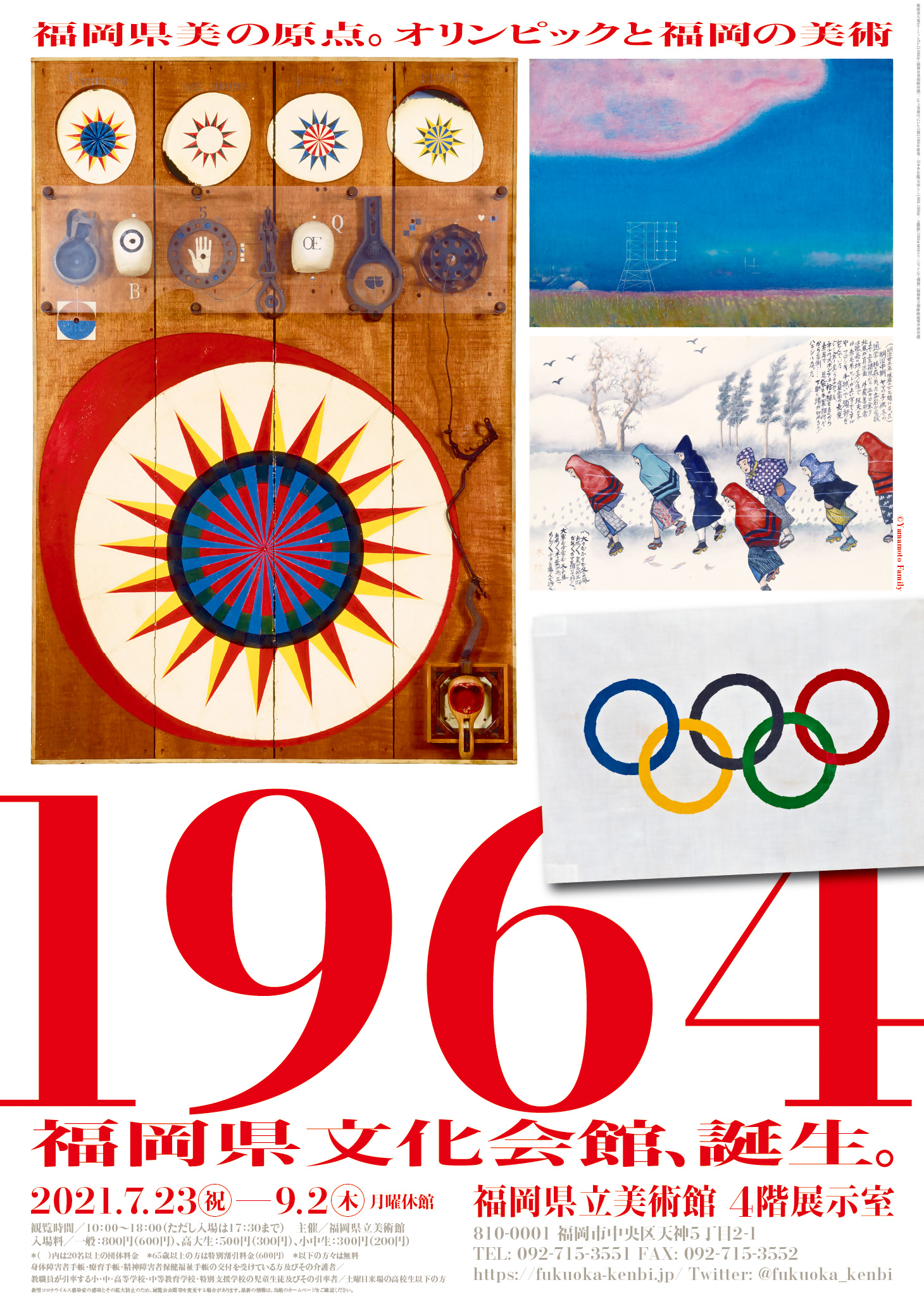
あと最近の「久留米絣と松枝家」(2024)は、展示構成から図録作りまで、色々やりきれたかな、という展覧会でした。これについては、松枝さんをはじめ、ご所蔵者さんたちも周囲の方々も大変協力的で、そもそも作品の持つパワーがとてもすごかったので、私はもうそれを並べただけなのですが。本当に作家さんの力をすごく感じる展覧会でした。
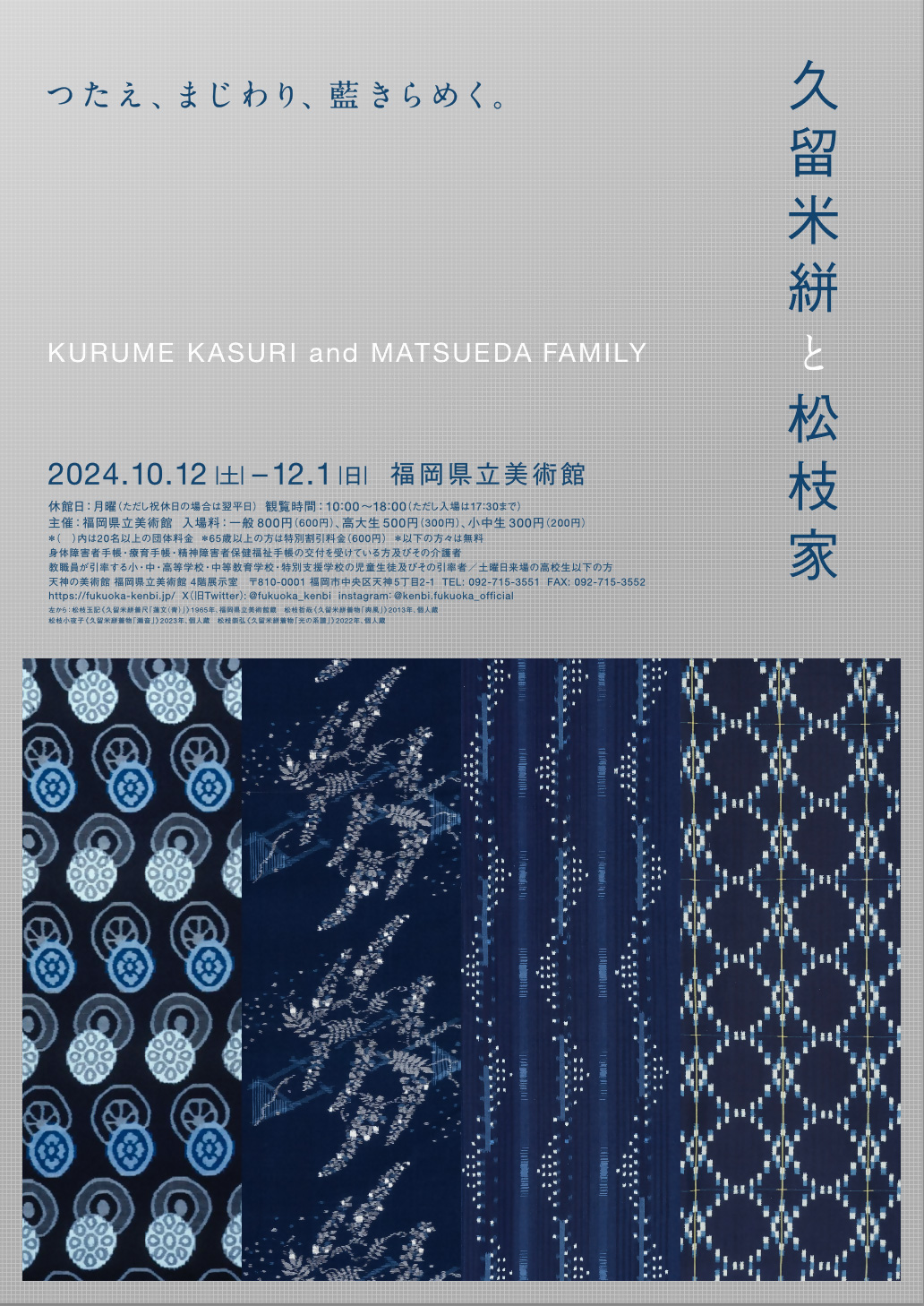
もうひとつだけ、私ばっかり続けてすみませんが、県美が毎年やっている「移動美術館展」についても紹介させてください。移動美術館展は、福岡県内の様々な文化施設へ県美のコレクションから名品をお持ちして公開する取り組みです。

私が担当したのは2022年度八女市での開催回だったのですが、すごく楽しく実施させていただきました。今まで諸先輩方からも、移動美術館展には色んな折衝や予算の調整などもあって簡単ではないとお聞きしていましたが、相手館の学芸員さんたちや八女の作家さん、地域の人たちや向こうの役所の方たちまで大変あたたかく迎えてくださって、あんなに縁を深められる機会になるとは思ってもみなかった、色々な広がりを実感できる展示になりました。
——僕も移動美術館展については、ぜひお伺いしてみたいと思っていました。県美が長年続けていらっしゃる企画ですが、あれはどのように開催が決定されるものなのでしょうか?
中島さん 先方からやりたいとご希望をいただくこともあれば、こちらから開催地側へ働きかけることもありますが、どこでやる場合にも、その地域の作家さん、開催時期の季節や行事、先方の展示室のサイズなども考慮しながら、ああじゃない、こうじゃないってやり取りを重ねて作品を決めていっています。

高山さん 数えたところ、今やっている芦屋町で40会場目でしたね(*取材時)。大体1年に1回の開催なんですけど、企画が立ち上がった当初は年間を通じて2回とかもっと回数をやっていた年度もあったようです。欠けることなく現在まで続けられていることも含めて、特別な取組みだと思っています。
——どうもありがとうございます。続いては、皆さんを悩ませてしまうことは承知のうえで、お一人ずつ、思い入れのある収蔵作品を教えていただきたいと思います。まずは、高山さんから。
高山さん さっきと同じようなことを言ってしまいますけど、収蔵品は基本的に全部可愛いんです(笑)。普段作品のことを「あの子」と呼んでしまうくらいどれにも愛着があるのは、三人共通だと思います。

ただ、強いてこの場でお応えするなら、児島善三郎の《静物》という作品が、私にとっては一番好きな作品と言ってもいいものかなと思っています。私が県美に入った年に、上司が私の大学時代の研究分野を考慮して、それならこの展覧会を担当してみたらいいんじゃない?と勧めてくださったのが、「児島善三郎と中村研一 福岡ライバル物語」(2012)という、2人を同時に紹介する展覧会でした。
展覧会の元となった魚里課長(当時)の構想を引き継ぐようなかたちで準備を始めてみたんですが、とはいえ初めての展覧会ということもあり、何をしたらいいのか? どこまでやれば終わりなのか? と、わからないことづくしで途方に暮れていたんです。

そんなときに、児島の収蔵作品の中からこの、赤をふんだんに使った華やかな本作が、辛いと感じていた当時の自分に元気を与えてくれるようなところがあったんです。展覧会が始まった後もこの絵を見れば元気になれると、本当に出勤するたびに毎日見に行くという自分の中のジンクスまでできあがりました。この絵は展覧会のポスターにも使ったこともあって、私にはその時のことを思い出させてくれる作品ですし、今見てもすごくワクワクするような色彩に魅了されてしまいます。私の中ではパワーを与えてくれる一枚として位置付けているような、大好きな作品です。
——ご自身の展覧会づくりの原体験に結びついた一枚という、とても素敵なエピソードですね。中島さんはいかがですか?
中島さん 「うちの可愛い子たち」という高山さんのお話も聞きながら、一番はじめに私が思いうかんだのは、「ケンビ・カワイイ・コレクション2022」(2022)という展覧会でメインビジュアルにした《瑠璃釉獅子形香炉》です。作家の名前も残っていない、誰が作ったのかも分からない平戸焼の、とっても小さな香炉なんですけど。丸っこい二頭身の獅子のかたちをしていて、頭の部分がパカッと取れて、その口から煙が出てくるようなつくりになっています。

現代の美術では、作品は基本的には作者ありきで評価されるものですが、工芸の分野では、作者が誰かということを問わずとも大切にされてきたものがたくさんあります。きっとこの香炉を作った職人さんも、はじめは「獅子の口から煙が出たら面白いだろうな」と思って作ったのだと思うんです。もしかしたら、中国とかに似た様なものがあって、それを着想源に作ってみたものかもしれません。
そういう人々の生活の中で生まれたいくつもの瞬間があって、それらを経て今日まで大事に伝わってきて、今では「作品」として扱われている。その一連がすごく「工芸っぽい」と感じられて、工芸担当としては胸が熱くなるんです。きっと工芸は今でも、そういう風に「こういうのがあったらいいな」とか「こういうのがあると素敵だよね」みたいな感覚から作られているものがあると思うんですよね。それは昔も今も、どちらにも通じるものだと思います。

——作品の向こう側に無数の人々の営みを見出していく、工芸ならではの魅力ですね。うーむ、どの方もエピソードが素敵で困ってしまいます(笑)。岡部さんはいかがですか?
岡部さん ひとつを挙げることは本当に難しいのですが、調査においてこのような表現があるのかと驚いたのは、江上茂雄の作品です。明治に生まれ、大正・昭和・平成を生き、生涯、自分が生きた町である大牟田と荒尾の風景を描き続けた作家です。

代表的なシリーズは、クレヨン・クレパス画です。限られた人しか大学に行けなかった時代、15歳から働いて家族を養い、いわゆる日曜画家として限られた時間を制作に充てていました。絵を描いていることをほとんど人に話すことなく、静かに自分の内面を積み重ね、絵画に昇華させていました。こうした画家の在り方を私は初めて知りました。江上茂雄の作品が福岡県立美術館にあることはとても大切なことだと考えています。

あともう1点挙げるとしたら、これは自分の専門分野とも通じていますが、彫刻家である安永良徳の煙草を吸うためのパイプです。このパイプは、安永が戦後シベリアに抑留中に、密かに制作しました。パイプの側面にはロシア語で「ここでの記憶は忘れない」「必ず帰る」といった趣旨のメッセージと作家のサインが刻み込まれています。
抑留という明日をも知れない過酷な状況の中、パイプに自身の存在を刻みつけるかのようです。そして、なんとか日本に持ち帰り、現在当館に収蔵されていることは奇跡的なことと感じています。引揚げの歴史がある博多港の近くに建つ当館として、安永のパイプを通じてそうした歴史をも語り得る、力強い作品だと思っています。

——前回記事で、開館以来の県美を支えてこられたお三方へのご取材でも感じたことですが、県美には他の美術館にも増して、人間一人ひとりの営みとその積み重ねを大切にされていく精神が確かに在りますね。いま、中島さんや岡部さんのご推薦される作品とそのエピソードをお聞きしていて、その思いを一層強くしました。
——最後に、お三方それぞれに、これから完成していく新県美への想いをお聞かせいただきたく思います。まずは、高山さんから。
高山さん 個人的には嬉しさ半分・不安半分というところですね。これまで、まるで「家」のような親密さでやってきたこの美術館のあり方を、今後は大きく変えていかねばなりません。その変化をどのように受け止め、運営していくのか。新しい美術館ではどのような展覧会をやっていくのか。そうやって色々考えていくと、やっぱりちょっと不安な思いももちろんあります。ただ、今まで展示室の狭さが原因で作品の点数や見せ方が限られていたものも、今後は色んなやり方が試せるようになることは非常に有難いことですし、とても嬉しいものだと思っています。

何よりも、念願の常設展をしっかり作ることができるのは、とても大きなことです。これまでは細々と髙島野十郎の特設コーナーなどで小さくお見せするしかできなかったのですが、やっと広く綺麗な展示室で、私たちの可愛い一万点のコレクションから厳選したものを、日々内容を変えながら見せていくことができます。
やっぱり美術館活動の肝は常設展にあるのだと、自分の美術館体験を踏まえても感じます。「あそこに行けばあの作品に会える」という、まさにそれぞれのお客様にとっての「お守り」みたいな作品を、来ればいつでも見られる場所に、やっとなれると思うんです。新しい美術館がそういう安心感の象徴みたいな場所になれたならすごく嬉しいなと思っています。
——続いて、岡部さんはいかがですか?
岡部さん 当館は、福岡県の美術を掘り下げることに丹念に取り組んできました。今後もその深度をいっそう深めていきたいと思っていますが、福岡県内のことだけではなく、国内外問わず様々な美術表現を紹介していくことで、来場される皆さんが、それぞれに豊かな感性を育んでいただけるような場になれるよう活動をしていきたいですね。また、新しい館では、作家さんが表現されたいことが実現できる場所にしたいと個人的には考えています。

——本当におっしゃる通りですね。最後に中島さん、いかがでしょうか。
中島さん 3番目ぐらいになってくると、もう自分が言うこともほとんど無くなってきちゃうんですけど、そうですね。まず施設が新しくなって、色々やれることや見せられるものが増えていくことについてはシンプルに「やったー」と思ってはいるんですが、そうは言ってもこっちの県美にもやっぱり愛着があるんです。行きつけのラーメン屋みたいな、ここにしかない居心地の良さというか(笑)。

新県美の話になるとどうしても、やれ新しいことをしなさいみたいな感じで話が進むというか、そうしなきゃ、みたいな気持ちにもなるんですけど、個人的にはまず施設が新しくさえなってくれれば、と思っているところもあります。というのが、これまで60年以上かけて育まれてきた現在の県美独特の親しみやすさは確かに良いものですが、一方でその敷居の低さが、作品や展示物が本来持っている価値を十分には伝え損ねさせていた部分もあると思うんです。そうした印象も、箱(=施設)が変わるだけでゴロっと印象が変わるなら、まずはそれだけでも大きいことだと思うんです。
だから新県美では、「こんなにいいものがあったんだ」ということを県民の皆様にも、そして外からお越しになった人たちにも見せられるような展示ができればと思います。実際、これまで色んな先輩方がやってこられた展覧会やそこで披露されてきたもののなかには、ただの一地方の美術には留まらないほど重要なものもたくさんあったと思うんです。やっぱり現実的にお金や設備を理由に諦めなくてはならなかった場面もたくさんありましたから、今後はそういった場面で少しでも踏み込める機会が増えるなら、この美術館が持っている本来の実力を、もっと広く伝えられると思っています。「県美はこんなもんじゃないぞ」、という気持ちです。

——確かに、新県美のことになるとつい「新しいこと」ばかりがフォーカスされてしまいがちですが、あくまでそこで実現されるものは皆さんがずっと続けてきた活動の先にしかないものですものね。その真価が今にも増して人々に広まっていくことを期待しています。本日は改めてお話をお聞きできて本当によかったです、どうもありがとうございました。
